✨言葉の大事さと生かされたことを再認識、ドラマ『舟を編む』を観て
最近、言葉を「ちゃんと選んで」使っていますか?
気づけばなんとなく、慣れた言葉ばかりを口にしていませんか?
最近、言葉を選ぶことの大切さを改めて実感させてくれるドラマに出会いました。
NHKで火曜22時から放送されている『舟を編む』です。
大まかなあらすじはファッション誌の編集部に所属していた主人公が、突然、辞書編集部へと異動になるところから物語は始まります。これまで感性やセンスを重視していた世界から一転、言葉一つひとつの意味や背景を深く掘り下げる世界へ。普段なにげなく使っていた言葉に向き合うことで、主人公の人間関係やコミュニケーションも少しずつ変わっていく姿が描かれています。
📚 言葉との出会いは、大学時代の「寮の先輩」から
私自身、高校時代までは本にほとんど興味がありませんでした。
しかし、大学時代に暮らしていた寮で出会った先輩の影響を受け、本の世界に足を踏み入れました。
当時、夢中になって読んでいたのは司馬遼太郎や宮城谷昌光などの歴史小説。登場人物のセリフや情景描写に力があり、読むたびに「言葉の力」を感じていたのを思い出します。
社会人になってからは自己啓発やビジネス書を中心に、1週間に1冊ペースで読書を続けました。そのため、語彙量についてはある程度自信がありました。
ですが――。
✍️「意味がわかる」と「使いこなせる」は違う
社会人6年目で営業から広報へ異動したことで、言葉への認識が大きく変わりました。
営業時代は「自分の思いをどう伝えるか」が主な焦点でしたが、広報では「自分の発信が社内外にどんな影響を与えるか」までを考慮する必要があります。そこで初めて、「言葉を選ぶことの難しさ」に真正面から向き合うことになりました。
「知っている」と「使える」の違い。
「伝える」と「伝わる」の距離。
言葉は思っていた以上に奥深く、繊細で、力強いものでした。
🌏 海外で教える中でも、言葉が支えに
その後、私は日本を離れ、中国へと渡ることになります。現地では、日本関連ビジネスを支える中国人スタッフに対して「ビジネス日本語」を教えるという、新たな挑戦が始まりました。
私には日本語教師の資格こそありませんでしたが、これまでの社会人経験を総動員して、自作の資料をもとに授業を行いました。最初は手探りでしたが、生徒たちは熱心に学び、少しずつ上達していく姿に私自身も励まされました。
言葉に悩みながらも、言葉によって繋がれた時間。
教える立場でありながら、私自身が言葉に生かされていたのだと思います。
💡 言葉があふれる時代だからこそ、言葉を磨く意味
現代はSNSなどを通じて、誰もが簡単に情報を発信できる時代です。
新しい言葉もどんどん生まれていますし、語彙が少なくてもコミュニケーションが成立する場面も増えています。
しかし、だからこそ**「しっかりした言葉を使うこと」の意味はむしろ大きくなっている**と感じます。特に今後、AIが生成する文章を人間が評価するような時代になると、言葉の読解力・判断力はますます問われるようになるでしょう。
『舟を編む』の登場人物たちが、一つの言葉を巡って何度も議論し、慎重に意味を選び取る姿を見て、私は昔の自分の経験と重ねながら「言葉とは何か」をもう一度考えさせられました。
🎁 おわりに:言葉は、人生に寄り添う「舟」になる
若い頃に比べて、私は今、言葉の価値を深く感じています。
それは単に「伝える手段」ではなく、ときに人と人とをつなぎ、考えを深め、人生に静かに寄り添ってくれるものです。
言葉選びに迷い、悩むこともありますが、そんな時間さえも「豊かだ」と感じられるようになった今、『舟を編む』というドラマに出会えたことに感謝しています。
📝 この記事を読んでくださった方へ…
皆さんは、最近「言葉」に向き合った瞬間、ありますか?
何気なく使っているその一語に、思いがけない重みや温かさがあるかもしれません。
ぜひ、あなたにとって大切な「ひとこと」があれば教えてください。

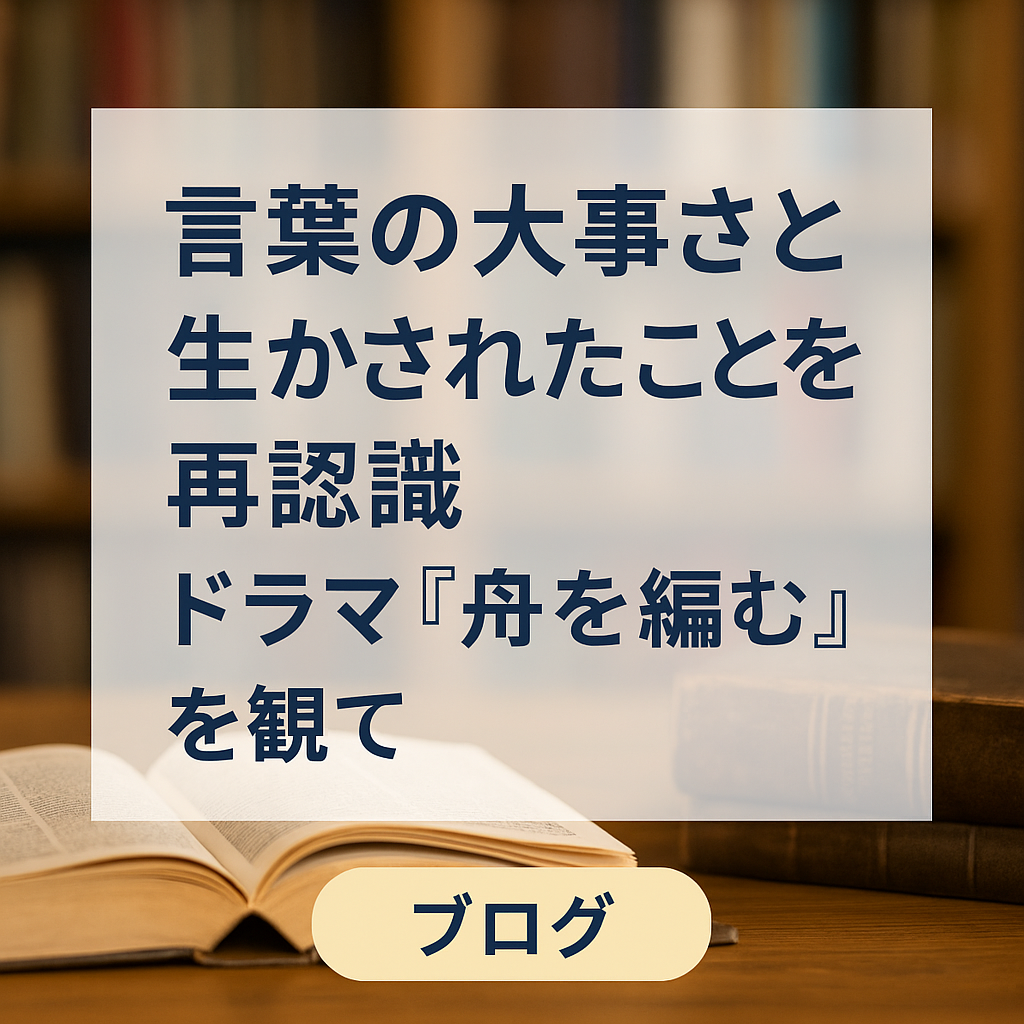
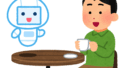
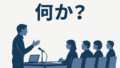
コメント