先日、2025年度の株主総会に2件参加してきました。午前中は電力会社A社の総会にリモートで、午後は陸運会社B社の総会に現地で参加。業態も運営スタイルも異なる2社に参加して、総会の雰囲気や内容の差に多くの気づきがありました。
この記事では、総会参加を通して私が感じたこと、そして「良い質問とは何か?」について考えたことをまとめてみたいと思います。
電力系A社の総会:活発な質疑応答と緊張感
午前中に参加したA社の株主総会は、昨年も参加している企業でした。そのため、ある程度予想していましたが、今年も活発な質疑が展開されました。
事前に株主提案もあり、当日も7〜8件の質問が飛び交いました。質問に対してはそれぞれの取締役が答える形で、真摯に対応していたのが印象的でした。特に原発に関する質問は避けず、これが国策レベルのテーマであることを踏まえつつも、会社としてのスタンスや考え方を丁寧に説明していました。
開始は10時で、終了は12時過ぎ。約2時間以上にわたる総会でした。
陸運系B社の総会:あっさり終わる静かな時間
午後からはB社の株主総会に会場で参加しました。こちらは今回初めての参加です。
会場の参加者はおよそ50名程度。スーツの人が多い印象でした。社長からの業績報告などが簡潔に行われ、その後の質疑応答では、質問者は一人だけ。事前提案もなかったため、全体的に淡々と進行し、15時に開始して30分ほどで終了しました。
「こういう形式もあるんだな」と感じつつ、同じ株主総会でも企業によってこんなにスタイルが違うものかと驚きました。
株主総会を通して感じた2つのこと
1. 取締役は大変だ
特にA社のように活発な質問が出る場合、取締役は想定内の質問だけでなく、思わぬ角度からの質問にも対応しなければなりません。しかも、それが公の場での公式発言となるため、言葉の選び方ひとつにも慎重さが求められます。
どの取締役も細かな質問にしっかり答えていて、「ご苦労様です」と思うばかりです。質問内容によってはその場で即答できないこともある中で、きちんと向き合う姿勢に誠実さを感じました。
2. 「良い質問」とは何か?
質疑応答を見ていると、質問の仕方にも差があることに気づきます。なかには「何が聞きたいのかよくわからない」「発言の目的が自己アピールに見える」と感じる場面もありました。
質問内容が要領を得ないと、会場からヤジが飛ぶこともあります。実際、そうした発言者が感情的になって場の空気が悪くなる一幕もありました。
とくに原発のようなテーマは、会社単体で判断できる内容ではないため、「取締役に聞いてどうするのか?」という違和感もありました。
私が考える「良い質問」とは?
株主総会に限らず、どんな場でも「質問力」は大切です。私なりに考える良い質問のポイントは、以下の4点です。
■ 端的であること
一文が長すぎると伝わりにくくなります。簡潔に要点を伝えることが、結果として相手の理解を助けます。
■ 最初に質問の構成を示すこと
質問が複数ある場合は、「3点あります」と最初に伝えるだけで、聞き手の負担がぐっと減ります。答える側への配慮は、良いコミュニケーションの基本です。
■ 他の参加者にも意味のある質問
自己満足の質問も悪くありませんが、多くの株主が興味を持つ内容であれば、総会の質全体が高まります。
■ 回答を促すだけでなく、新たな視点を与える質問
その場で答えが出なくても、「考える価値がある」と取締役に思わせるような質問こそ、建設的で価値のあるやりとりになると思います。
質問は「対話の力」
質問とは、単なる情報収集ではなく、対話のきっかけであり、その人の思考力や視野を映すものだと思います。良い質問は場の空気を引き締め、話の質を深める力を持っています。
私自身、これからも株主として企業の成長を見守ると同時に、「良い質問とは何か?」を自分の中で磨いていきたいと思っています。

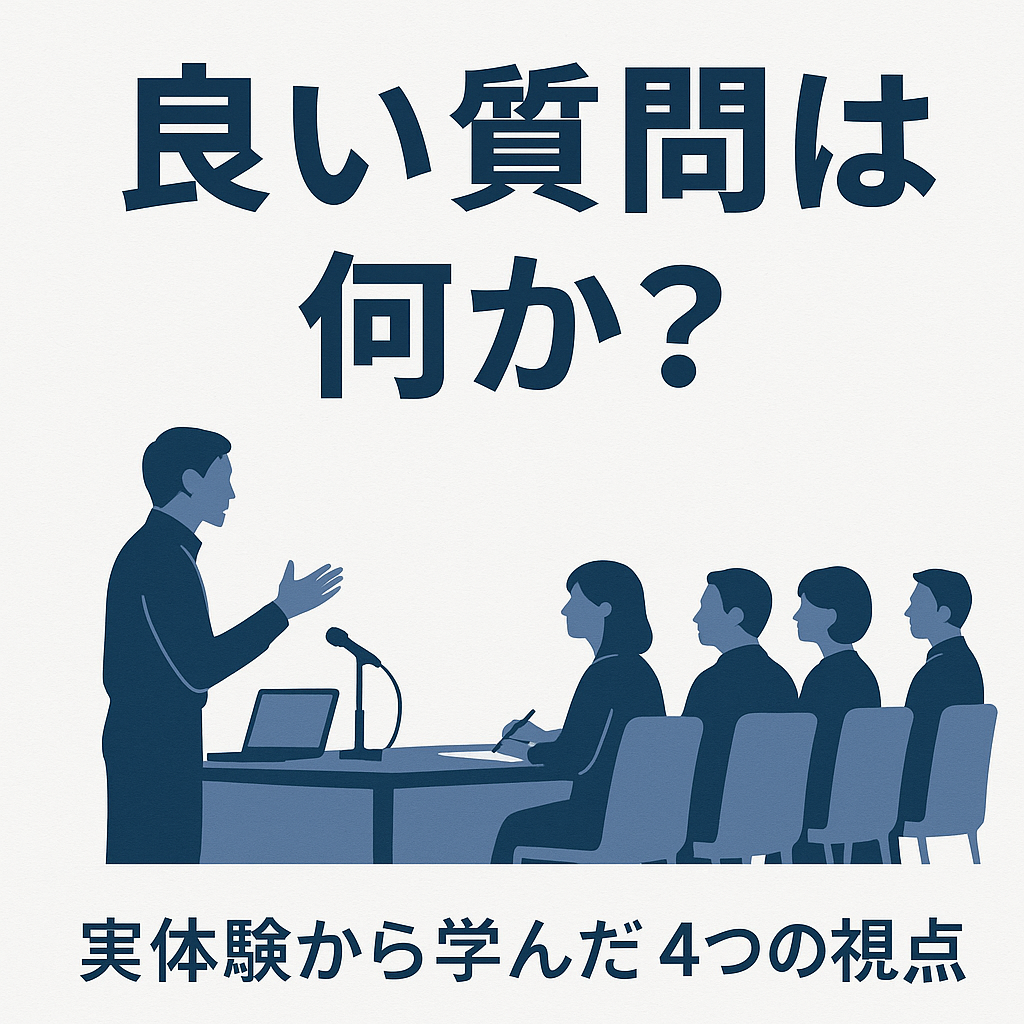
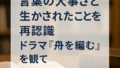

コメント